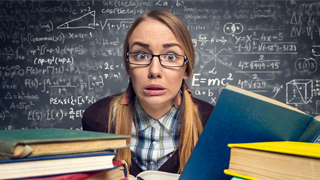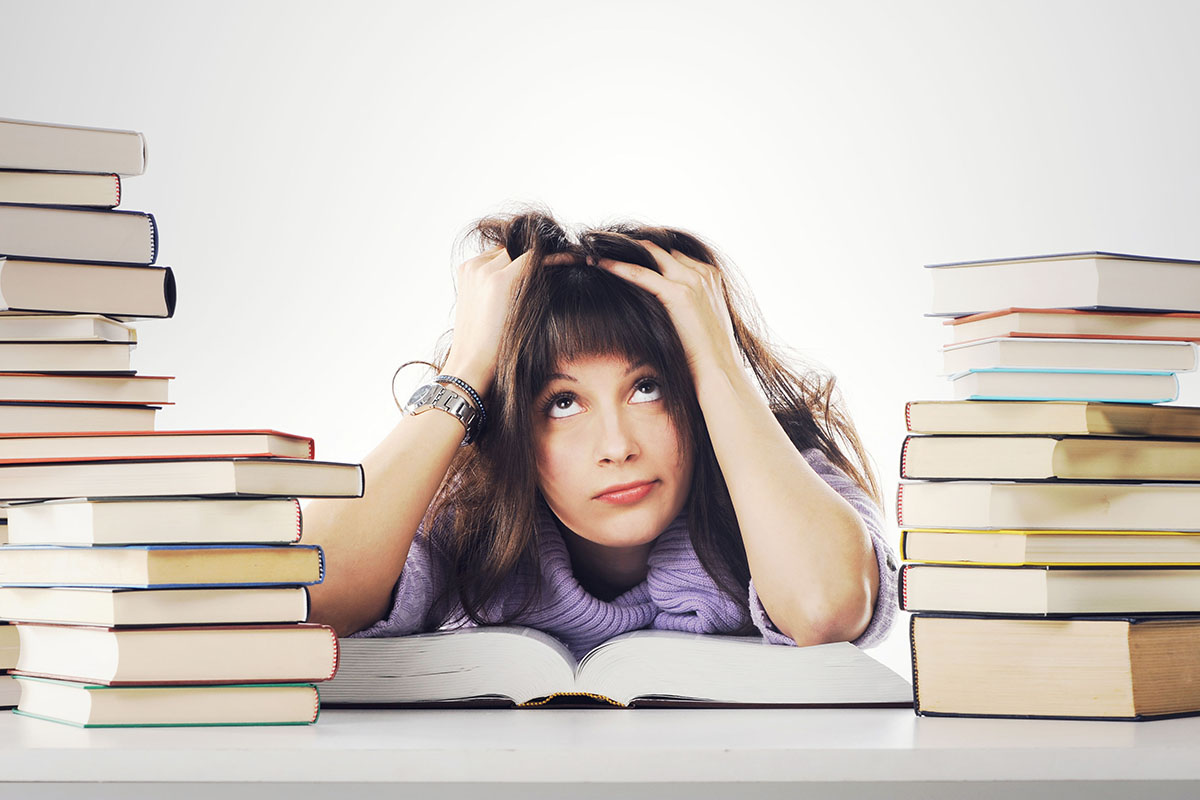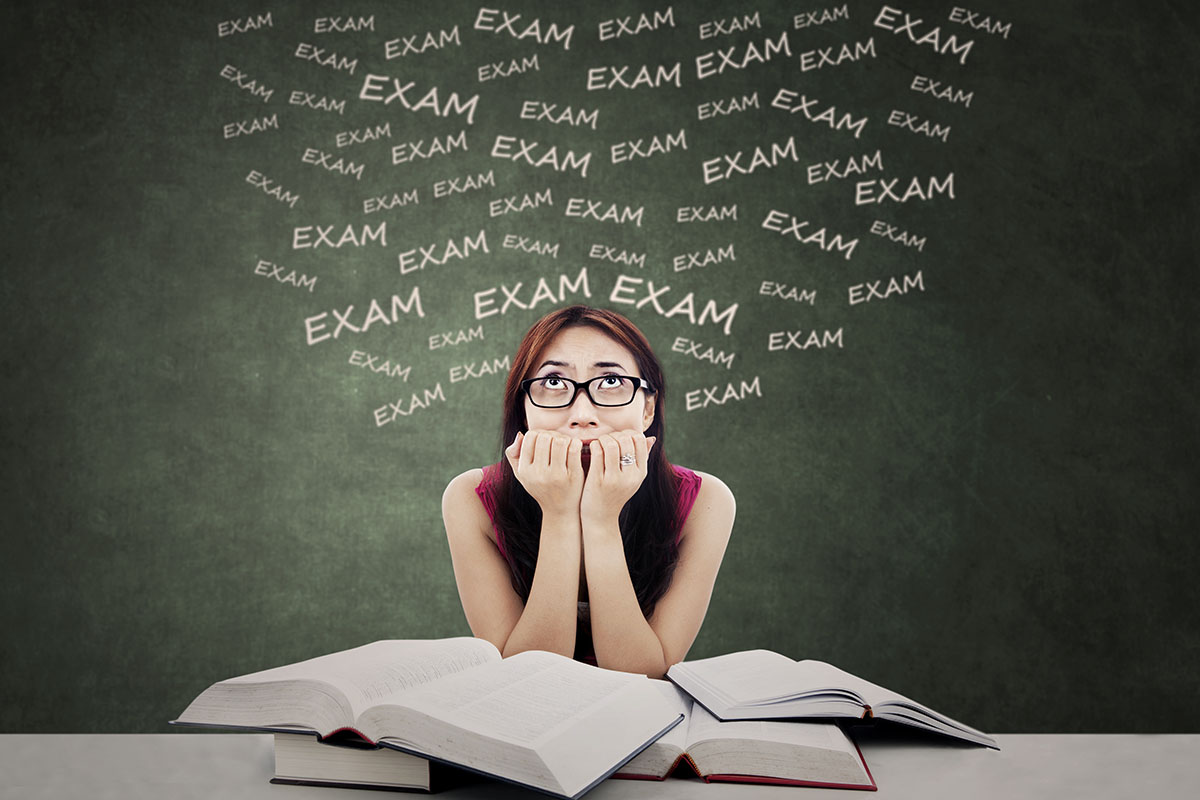SERVICE CONTENT
服务内容
YOUTH PSYCHOLOGY ZONE
青少年心理专区
EXPERT TEAM
专家团队
关爱青少年心理健康
从心 开始
-

成瘾问题
《青少年成瘾行为调研报告--基于2017/2018青少年健康行为网络问卷调查数据分析》的结果显示:尽管我国大多数青少年每天玩游戏的时间不超过三小时,依然有18%的青少年,玩电子网络游戏超过4~5个小时。按照世界卫生组织的判断标准,我们会认为,每周玩游戏超过5天,每天超过5小时就很可能是成瘾行为,也就是说我国有1/5的青少年已经有游戏成瘾现象或面临游戏成瘾的风险。2021-10-18
-
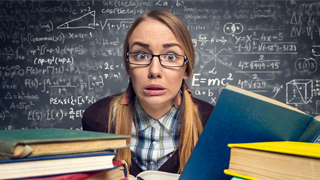
青少年强迫
青少年强迫症的表现具有强迫型人格,其主要表现是主观任性、急躁、好强、固执、自制力差,或者性格内向、胆小怕事、优柔寡断、迟疑畏缩、于是过于谨慎、严肃、认真、顺从、缺乏自信、墨守成规、呆板、喜欢过细的思考问题、追求完美等。2021-10-18
-

青少年焦虑
焦虑是对自己或者重要他人的生命安全、前途命运等的过度担心而产生的一种烦躁情绪。其中含有着急、挂念、忧愁、紧张、恐慌、不安等成分。它与危急情况和难以预测、难以应付的事件有关。事过境迁、焦虑就可能解除。有人并无客观原因而长期处于焦虑状态,常常无缘无故害怕大祸临头,担心患有不可救药的严重疾病,以致出现坐卧不宁、惶惶不安等症状。2021-10-18
-
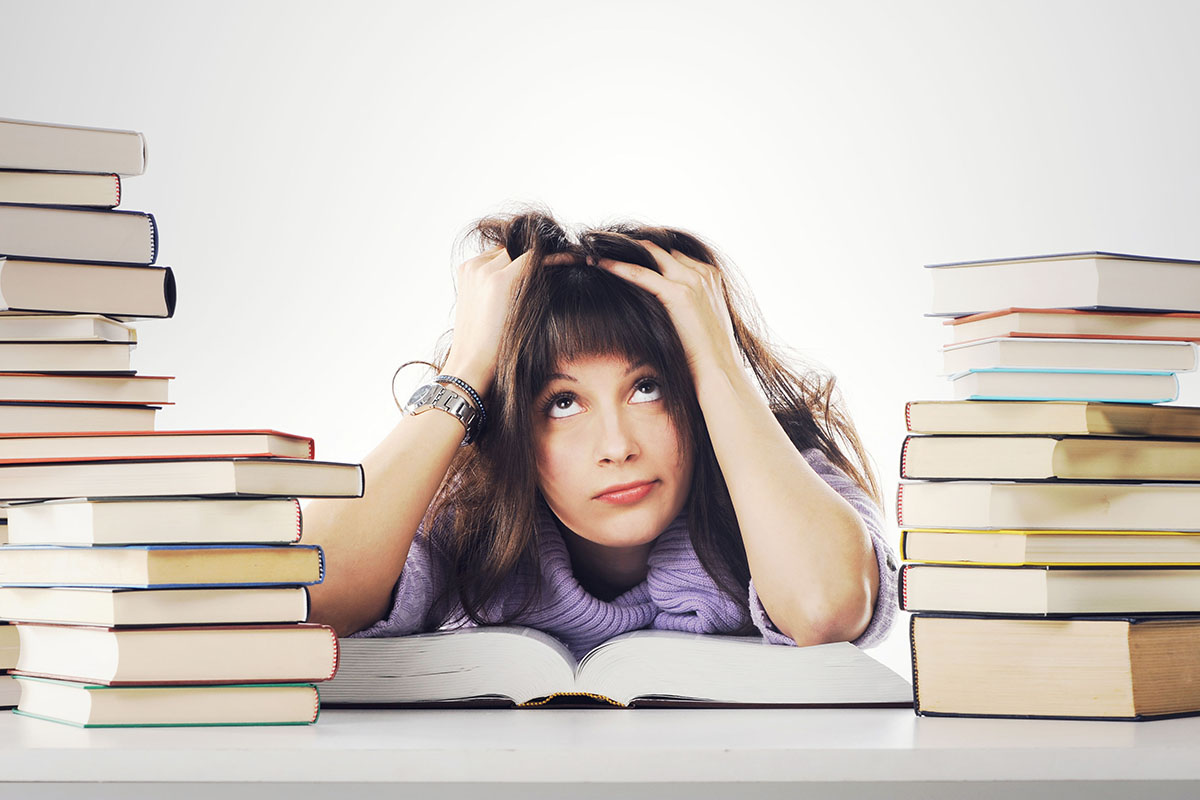
青少年厌学
厌学是学生对学习的负面情绪表现,从心理学角度讲,厌学症是指学生消极对待学习活动的行为反应模式。发展心理研究表明,学习活动是学龄儿童的主导活动,是儿童社会化发展的必要条件,也是儿童获取知识和智慧的根本手段。2021-10-11
-

亲子冲突
亲子冲突主要集中在青少年阶段,也就是我们常说的 “青春期”。青春期是个体由童年向成年的过度时期,常常被戏称为“疾风暴雨期”和“亲子关系危机期”。2021-10-11
-
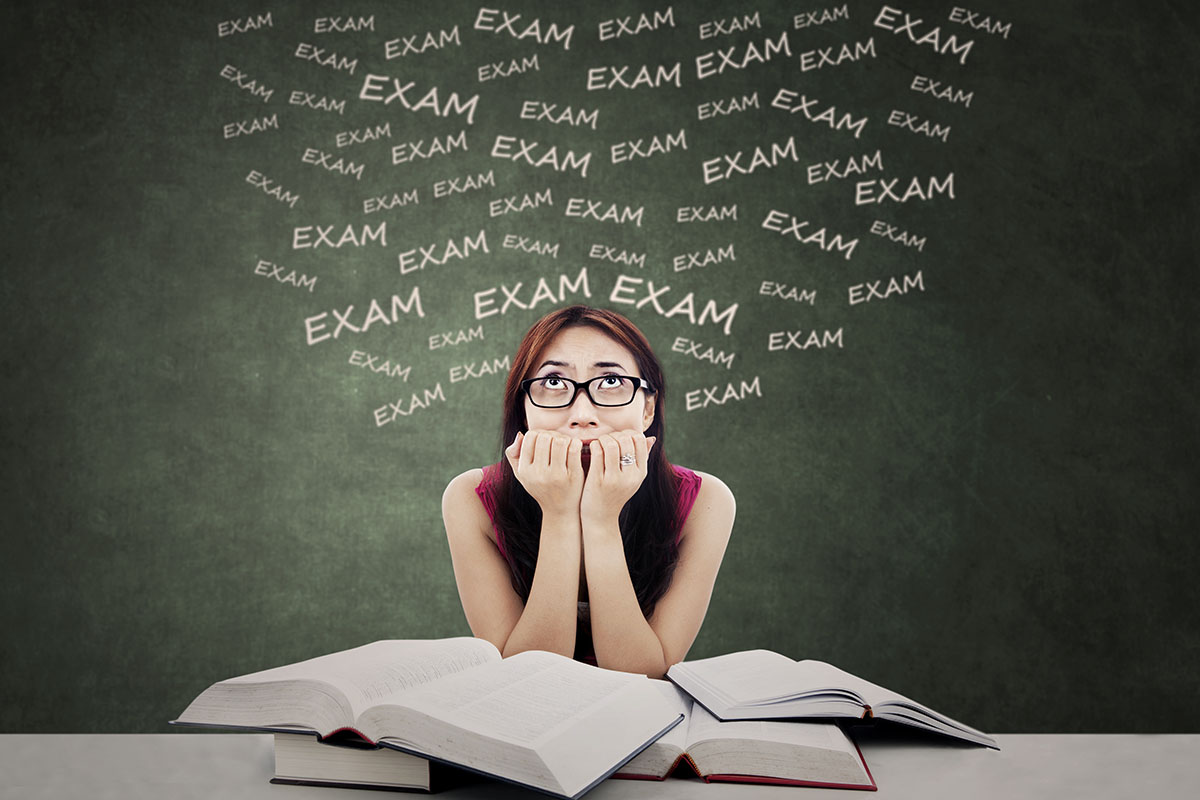
中高考减压
中高考的对初三、高三的孩子来说是压力很大的一个压力源,在备考的时候,孩子们总是负担着很大的压力,一部分是由于外部因素,还有一部分是因为自身因素,无论是什么原因,由于孩子们的心理素质能力还不高,如果没有办法调整自己的压力,就有可能激发他们的不良情绪甚至不良行为的发生,所以我们一定要重视考前压力这个问题。2021-10-11
-

青少年抑郁
据2016年官方统计数据报告显示,我国的抑郁症患者已经超过一亿。也就是说,平均13个人里,就有一名抑郁症患者,有更多的人是徘徊在抑郁症边缘,处在抑郁状态中,更多的人也会经常有抑郁情绪。青少年的抑郁人数这几年有不断攀升的趋势。2021-10-18
-

青春期性心理
青春期性发育过程中,青少年产生的性心理问题比较多,这些问题基本都属于认知调节方面的问题,但由于其带有隐蔽性,加上社会的忽视与个体的掩视而不易被发现,如果严重发展下去,就会发展成各种性心理障碍和疾病,严重影响他们的身心健康,影响正常的学习、工作与生活,造成不良后果。2021-10-18
-

青春期叛逆
叛逆期是指青少年正处于心理的过渡期,其独立意识和自我意识日益增强,迫切希望摆脱成人(尤其是父母)的监护。他们不满父母把自己当小孩,会把自己以成人自居。为了表现自己的“成熟和特别”,他们也就对任何事物都倾向于批判的态度。正是由于他们感到或担心外界忽视了自己的独立存在,叛逆心理才因此产生,从而用各种手段、方法来确立“自我”与外界的平等地位。2021-10-11
PSYCHOLOGICAL INFORMATION
心理资讯
- 2025-05-21
- 2025-05-16
- 2025-05-06
- 2025-04-23
- 2025-04-22
- 2025-03-29
- 2025-03-28
PSYCHOLOGICAL COUNSELING GUIDE
心理咨询指南
- 2021-10-22
- 2021-10-22
- 2021-10-22
心理咨询中
- 2021-10-27
- 2021-10-22
- 2021-10-22
心理咨询后
- 2021-10-25
- 2021-10-25
- 2021-10-23
心理咨询前
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 18910727291
-
ꁗ 43442237
-
ꀥ 微信客服

茁达心理作为专业的茁达心理咨询机构,为您解决各种孩子青春期、厌学等问题,欢迎来电咨询:茁达心理咨询的客服-王老师。
心理服务
心理专家
联系我们
扫码咨询茁达心理老师
友情链接: